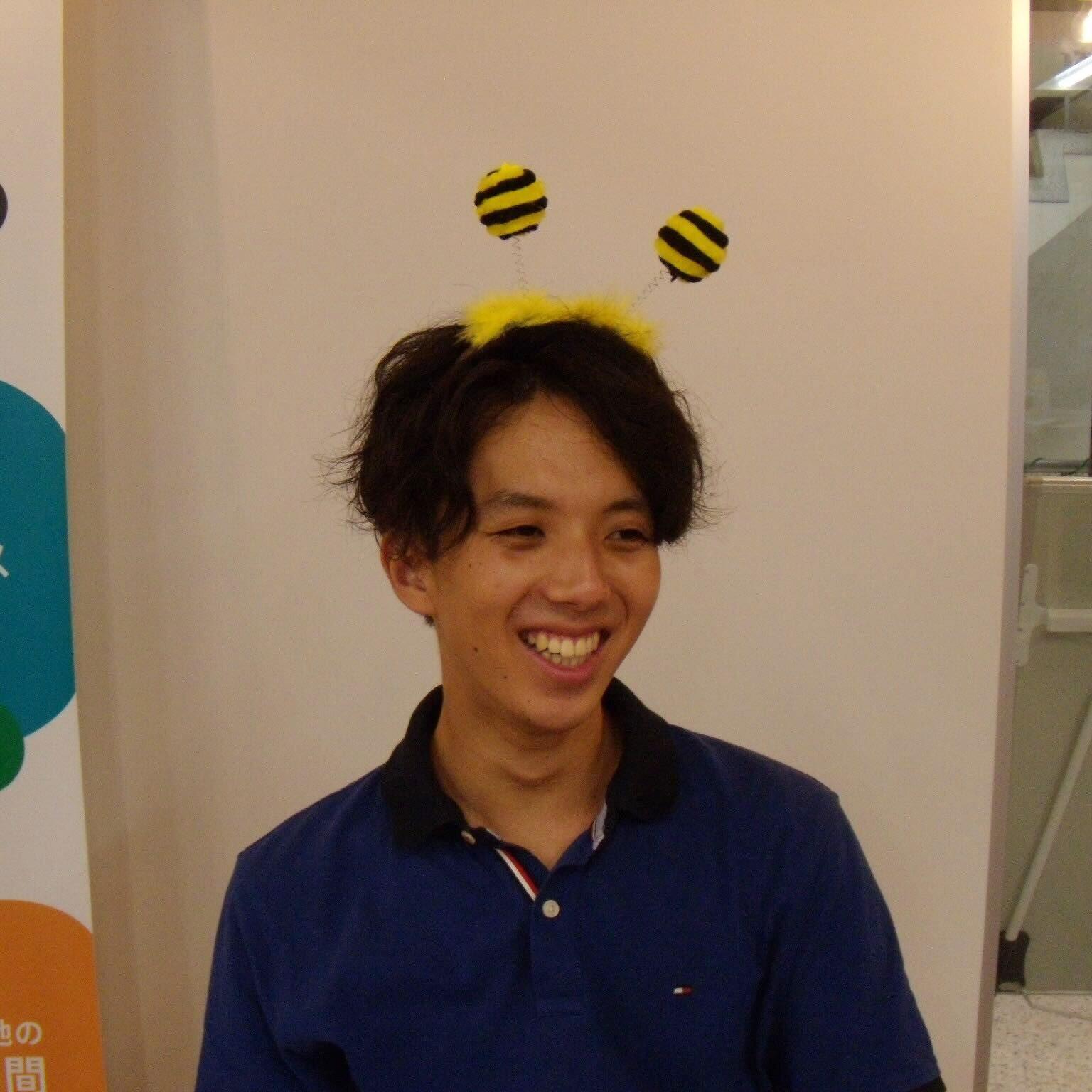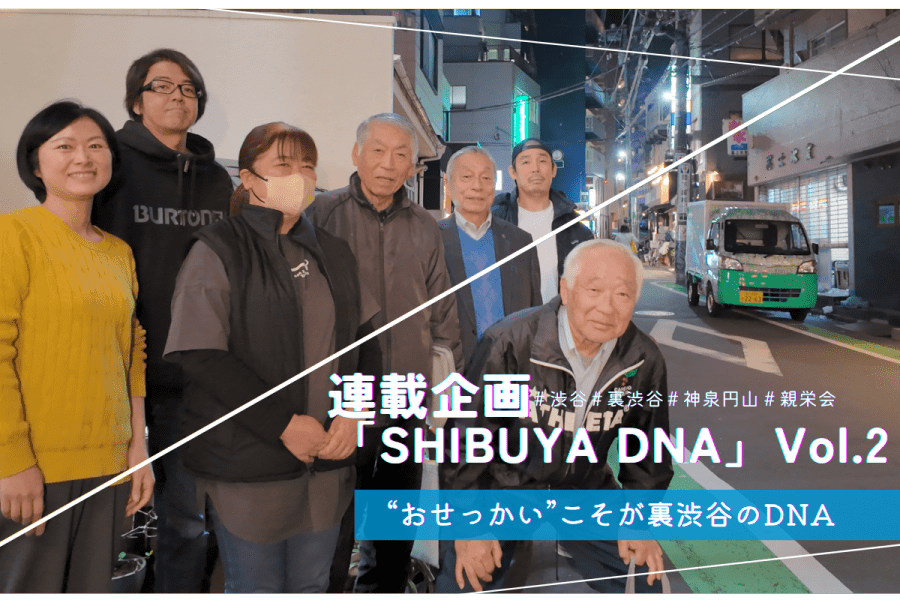渋谷ヒカリエ11階にある展望フロア『スカイロビー』。再開発が進む渋谷駅周辺、今しか見られない景色を絶好のロケーションから眺めることができます。
そんなスカイロビーの一角に、ひとつの模型が展示されています。再現されているのは、大小さまざまな建物がひしめき合う渋谷駅周辺の街並みです。普段は地上から見上げているこの景色を見下ろすという経験は新鮮で、思わず見入ってしまいます。一体、この「渋谷駅周辺地域都市模型」はいつ、どんな目的で作られたものなのでしょうか。
今回は、かつて模型の作成に関わっていたという早稲田大学非常勤講師で都市計画研究者、前UR都市機構職員・芦野光憲さんにお話を伺いました。

模型を通して、渋谷の街の未来を創造してほしい
2005年、渋谷駅周辺は『都市再生緊急整備地域』に指定されました。都市再生緊急整備地域とは、都市の再開発を促進し、経済活動を活性化させるために国が政令で指定するエリアのこと。指定されることで、規制緩和やインフラ整備の支援を受けられ、大規模な都市開発を円滑に進められます。
この指定を受けた後、渋谷駅周辺ではさまざまなプロジェクトが本格的に動き出しました。東京メトロ副都心線の開通(2008年)や旧東急文化会館跡地(現在のヒカリエ)の開発(2012年竣工)。そんな中、2007年に社会実験として開催されたのがSHIBUYA INFOBOX展です。
「当時、都市再生緊急地域への指定に関する地元の方への情報提供、そして今後渋谷駅周辺で展開される再開発の機運を醸成する場が必要だと感じていました」
SHIBUYA INFOBOX展は2007年10月8日~11月4日、渋谷マークシティウェスト4F クリエーションスクエア(当時)で開催されました。正式なイベントタイトルは「『SHIBUYA INFOBOX』~渋谷のまちづくり情報発信基地〜続く街。過去から現在、そして未来へ」。
渋谷の時間の変化を体験できる場所をテーマに、こどもがまちづくりをビジュアルで学べる『バーシャルシティSHIBUYA』や地下鉄渋谷駅の模型、渋谷の風景の変化が感じられる『渋谷今昔物語』などが展示されました。そして、その中の一つとして生まれたのが『渋谷駅周辺模型』(現在の「渋谷駅周辺地域都市模型」)です。

模型のスケールは1/500。当時はまだドローンのような技術がなく、実際の街並みを忠実に再現するために、多くの関係者でさまざまな工夫と試行錯誤を重ねたといいます。
「まず範囲内のビルを四方向から撮影し、それぞれの形に合ったスチロール状の素材に写真を貼り付けます。そして、完成したビル模型を写真地図の上に配置し、渋谷の街を立体的に再現しました。現在は竣工されている大規模な建築物についても、随時更新され、街の姿が分かるよう模型として組み込まれています。模型を通し、都市再生緊急整備地域に指定されたエリアの『現在』を見渡し、一人一人の思い描く『未来』を創造してほしいという思いが込められています」



イベントの総来場者は約4,000名。地元の方も多く訪れ、好評を博しました。企画を進めるにあたり、芦野さんはフランスの都市計画の手法も参考にしていたといいます。
「当時、フランスの都市再生について研究しており、都市開発やLRT(次世代型路面電車)導入の協議における『コンセルタシオン』という手法を知りました。これは、開発予定の模型展示などをモチーフに行政や開発事業者、市民が対話しながらまちづくりを進める手法です。渋谷でも、市民が自分の街について考え、意見を持つきっかけとなる場を作れないかと考えました。写真と模型を使い、渋谷の歴史や現状を俯瞰することで、まちづくりへの関心を高めることを目指したのです」
渋谷の魅力が失われてしまうのではないか
静岡県出身の芦野さんは、高校生の頃から都市計画に強い関心を持っていました。
1980年に早稲田大学理工学部に入学し、1986年に同大学院理工学研究科都市計画部門を修了。一貫して都市計画を学び続けました。卒業後は、「都市計画を実践したい」という思いから、現・独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)に就職します。
「UR都市機構では36年間、公民連携の都市計画や都市開発事業に携わってきました。横浜みなとみらいや多摩・港北ニュータウン、さいたま新都心公園、さらに東京臨海部の東京オリンピック2020大会施設のまちづくり審査など、さまざまな事業の構想・計画・審査などを担当してきました」
2007年当時はUR都市機構から民間都市開発推進機構へ出向していた芦野さん。旧東急文化会館跡地の民間都市開発支援を担当していたことがきっかけで、SHIBUYA INFOBOX展にも関与していました。
「18歳で上京してきた私にとって、渋谷は憧れの街でした。若者が映画館の情報誌を片手に散策する、そんな活気あふれる街だったんです。ところが2000年代に入り、バブル崩壊やリーマンショックの影響、さらには戦後建てられた建物の老朽化が進み、1980年代の賑わいが戻らない光景を目にしました」
このままでは、渋谷の街としての魅力が失われてしまうのではないか。そんな危機感を抱いていた芦野さんは、防災の観点からも課題を感じていたといいます。
「スマトラ沖地震をきっかけに、渋谷の防災施設についても考えるようになりました。特に旧東急文化会館跡地には、災害時の対応力を高めるための機能が必要だと感じていました」
結果として、防災機能を備えた都市拠点として誕生した渋谷ヒカリエ。渋谷区防災センターをはじめ防災機能を持つ施設が整備され、渋谷区区民サービスセンターや生涯活躍ネットワーク『シブカツ』などの公的な施設も併設されました。
「渋谷の再開発では、非常時に備えた防災機能と、日常の暮らしを支える施設の両方が整備されてきました。こうしたフェーズフリー(平常時と非常時の垣根をなくすこと)の考え方が根付いていることはとても心強いですね」
18年間、引き継がれる思い
そんなヒカリエで展示されている『渋谷駅周辺地域都市模型』。現在も多くの関係者がメンテナンスやバージョンアップを行い、新しい建物ができるたびに更新が続けられています。展望フロアから見下ろす実際の街と見比べながら、外国人観光客への説明にも活用されているといいます。
現在は早稲田大学理工学術院で非常勤講師を務めている芦野さん。都市計画を志す学生の育成に力を注いでいるといいます。
「渋谷区まちづくり第二課、同区教育委員会地域学校支援課、こども科学センター・ハチラボの協力のもと、都市計画を学ぶ大学院生に向けて、模型をモチーフにした『まちづくり科学教育』を実践しています。さらに、横山さん(一般社団法人渋谷再開協会参与)らに協力して、区内の小学生に対してもSTEAM教育に資する「渋谷科学アカデミー・渋谷のまちを科学する」講座を支援しています。参加した小学生からは『模型の精巧な作りに驚いた』、大学院生からは『街を俯瞰して見ることで、新たな視点で渋谷を捉えられた』『都市計画・観光・防災・教育・データ活用など、多岐にわたる分野での活用が期待される』という声をいただいています。模型を通し、参加者一人一人が未来を創造することを学んでいると感じています」
「今もこうして多くの方に見ていただけること、そして“まちづくり科学教育”という新たな役割を持つようになったこと。模型を作成した18年前には想像もしていませんでした。これは、単なる模型というだけではなく、地元の方々が維持・管理・更新し、変わりゆく街と比較でき未来を創造することを学べるからこそ、生まれた価値だと思います。こうした取り組みが全国に広がり、それぞれの地域に合った形で活用されることを期待しています。そして、いつか日本の都市計画やまちづくりの礎の一つとなってほしいと心から願っています」
ーー取材を終えて
以前から好きでよく見ていた『渋谷駅周辺地域都市模型』。まさか18年も前に作られたものだとは知りませんでした。僕の一つ年下のこの模型。これからも、その成長を見守っていきたいです。
今や『100年に一度の再開発』とも言われ、世界から注目を集める渋谷の街。しかし、ほんの20年前には勢いを失い、苦境に立たされた時期があったという事実には驚かされました。街の“価値”をどう高めるのか。再開発に関わるさまざまな人の思いに触れられたことがとても嬉しかったです。
開発が一段落したその先、今度は渋谷の“魅力”をどう育んでいくのか。これからは僕たちが考えていきたいと思います。
◾️芦野光憲さん プロフィール
早稲田大学理工学術院 非常勤講師/都市計画研究者
1986年、早稲田大学大学院理工学研究科都市計画部門を修了後、現•独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)に入職。36年間にわたり、公・民連携による都市計画や都市開発事業に従事。渋谷駅周辺再開発、東京臨海、横浜みなとみらい、千葉蘇我臨海、さいたま新都心、ニュータウン、大学立地まちづくり、産業団地、防災公園、東日本大震災復興支援、など、全国の都市計画・開発に携わる。
2008年、早稲田大学にて博士(工学)を取得。中心市街地活性化、都市再生、低炭素まちづくり、エリアマネジメント、まちづくり科学教育プログラムなどの研究を行う。経済産業省・国土交通省の中心市街地活性化診断・助言委員他歴任。「世界の都市再生」(共著)他執筆。東京オリンピック2020大会施設の有明北まちづくり委員会副委員長としてまちづくり審査にも関与した。
現在は、早稲田大学理工学術院の非常勤講師を務め、都市計画の研究や後進の育成に取り組んでいる。