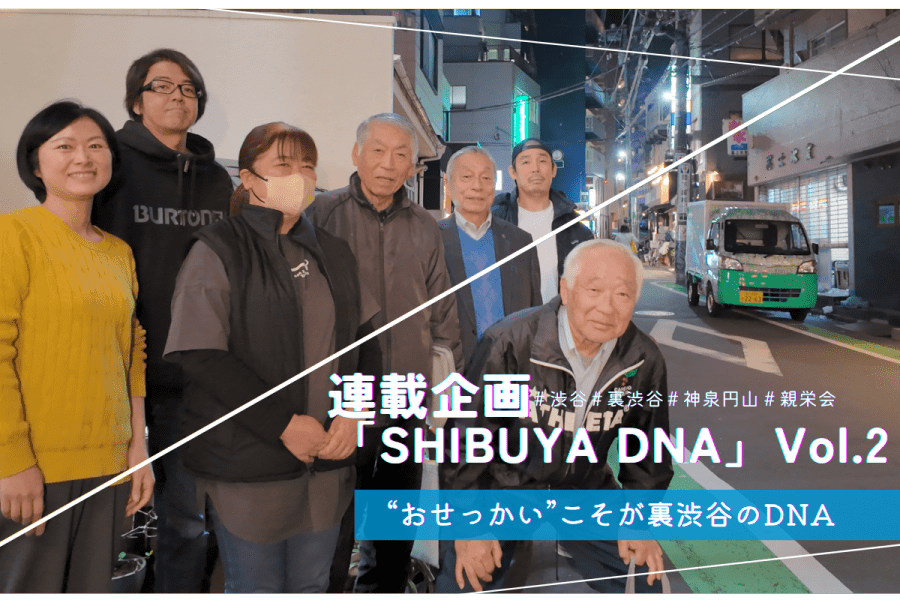公園通りとその周辺エリアのデザインを提案するコンペ「渋谷公園通り2040デザインコンペ」にて最優秀賞を受賞した建築家の津川恵理さん。パフォーマンスを通して身体表現する仕事に就きたかったという中高時代、そこから建築家への道へ進んだと言います。なぜ建築の道に進んだのか、建築を通じて何を表現するのか津川さんに迫ってみました。
パフォーマーになりたかった。そして建築の道へ
津川さんにお会いしたのは渋谷公園通り協議会の会合の後。まさにこれからの渋谷公園通りの街をどうしていこうか話し合っている場所。緊迫した雰囲気なのかと思い、恐る恐る扉を開いたら、津川さんの人柄からか部屋はとてもリラックスした空気。優しい物腰と同時に、キリッとした視線で落ち着いた雰囲気が津川さんの第一印象でした。筆者と同郷の神戸出身ということもあって、まずは生い立ちについて聞いてみました。

「中高時代は学校以外の時間で、ずっと独学でダンスの勉強をしていました。人間の内面性が現れる身体表現に惹かれて、それを研究したいって純粋にずっと思っていて。本当は身体表現者の道に行きたくてオーディションなども受けていたんです。
神戸出身の神戸育ちで、勉強熱心な家庭で育って中高一貫の進学校に通っていました。そんなこともあって親を説得できなかったので、身体表現の道からは一度離れて、大学に進学することにしたんです。大学の学科の中でもクリエイティブな力を発揮できるのは建築かな?と思って京都にある大学の建築学科に進学しました。
それでも身体表現への熱は冷めずに、大学時代もアルバイトで稼いだお金でダンススタジオのプロ育成コースに入って、多いときだと1日に10時間くらいダンスを踊っていました。
大学院からは東京に出てきて早稲田で建築を専攻したのですが、そこでも身体表現を諦め切れなくて。最後の修士設計の時に、身体表現と建築を結びつけた公園の設計をしました。
そこから身体と結びついた空間を都市空間に作っていくことに興味を持っていきました」

▲サンキタ広場 <撮影:ⓒ生田将人>
「大学院修了後は3年間、東京の組織設計事務所で勤めて、その後文化庁の派遣でニューヨークにある建築設計事務所Diller Scofidio+Renfro(DS+R)で修行を積みました。DS+Rはマンハッタンにあるハイライン(高架線路跡を空中庭園にリノベーション)など公共空間や建築などを手がける設計事務所です。DS+Rでは建築設計だけでなく、プラダのバックや都市型演劇などのデザインにも携わりました。
ちょうどNYでの生活が終わるタイミングで、生まれ故郷の神戸三宮駅の駅前広場のデザインコンペがあったので応募したら採用されました。帰国したタイミングで独立して建築設計事務所『ALTEMY』を立ち上げました」
コンテクストをとらえて設計していく

▲まちの保育園 南青山 <撮影:ⓒGION>
津川さんが手がける設計は、建築だけでなくて多岐に渡ります。どのような領域の設計をされて、設計をする際にどのようにアプローチしているのか聞いてみました。
「駅前広場などのランドスケープや建築空間だけでなくて、西陣織の織物の展示空間、さらには都市の移動空間や舟などのデザインもしています。ただ、建築家と名乗っているところにもこだわりがあって、設計対象が建築でないときも、都市や社会のコンテクストを捉えながら、歴史の縦の軸と、現代の横の軸が交わる設計をしていきたいと思っています。
大事にしているのは人間の内面性が表に現れるような瞬間を設計することです。何もかもが便利になりすぎた現代では、身体が受動的になっていると思います。
自分で主体的に環境を構築していくような、本来持っていた人間力を今一度取り戻していけるような空間、つまり人が生き生きしている都市空間を作っていきたいと思っています。
公共空間だからと過ごし方を大きな型にハメるのではなく、個々人がバラバラになり、それぞれの過ごしたいように過ごせる、そんな状況や場所をどうやって作っていこうか常々考えています。
今の都市空間の中では、利便性や合理性など資本中心で成立しているところがあるので、本来人によってそれぞれ違う快適性とか、その人の欲望が出てくるような街をつくっていきたいです」
渋谷公園通りについて
神戸、京都、ニューヨーク、東京といろんな特徴を持った都市に住んできた津川さん。公園通りを設計するに当たって、渋谷の都市空間についてどのように感じているのでしょうか?
「私がこれまで住んできた場所で、東京以外の神戸、京都、ニューヨークはグリッド状の都市なんですよ。地形と方角がものすごい身体的に一致してるんです。
東京、特に渋谷は歩いていても方角がわからなくて戸惑ったんですが、設計するにあたって都市の成り立ちを研究しました。そこには、独特の地形があって、その上に都市が出来上がっていった、そんな歴史を知るととても特徴的な背景がある街だと思います。
渋谷は駅周辺は谷地ですが、すぐ近くの山の上に松涛や青山などの住宅地があり、そういう場所とのインタラクションで独自の文化が育っていったんだと思います。
渋谷系っていう音楽が出てきたように、何かメインストリームには吸収されない独自の文化が育つ場所です。
魅力的なコンテンツで溢れるネット社会が加速していますが、現実の都市だから起こる文化がしっかり育つよう、街をつくっていきたいと思います。
70年代や80年代の公園通りの写真を見ると、パルコの前で佇む人がいたりしています。
今は人が多くて、渋谷の中でも安心して憩える場所が少なくなってきていると思います。
渋谷独自の文化を作ってきたっていうプライド『カルチャープライド』をいかに捨てずに持ち続けて、しかもそれが新しい技術と合わさって、イノベーティブに発展していくか。人を消費する街ではなく、人によって育つ街が面白いと思います。そんな思いで今回のデザインコンペに参加しました」
津川さんが描く未来の渋谷公園通り
最後に今回の公園通りコンペの提案内容について聞いてみました。

「実は京都の学生時代から、プチ公園通りにあった古着屋さんに通っていたり、公園通りは思い入れがある場所なんです。
今回のデザインコンペで提案したのが『触れる都市のマチエール』。マチエールというのは美術の世界では素材の質感を意味する言葉として使われます。道路にちょっとした凹凸のある微地形を作って、舞台となるテアトロン(シアターの語源になった言葉)を設計しました。ここに集まる人がカルチベートされていくような状況を作る。そのための場所を、道路にテアトロンという形で用意するっていう提案です。
公園通りに行ったら、いつも何か違うことが起こってるよねとか、何か人が座ってて楽しそうな風景が街に広がってるなみたいな、人が日常の中で何か文化を生んでいるという状況を、道路空間に表出させていくようなイメージしてデザインしました。
東京に住む若者でも、東京で文化を作っていこうとする、ミュージシャンとか小説家の方とか、ファッションデザイナーの方とかがここに来ると何か知らない世界を知ることができるみたいな、そんな街になったらめちゃくちゃ面白いと思います」


インタビューを終えて
ご自身がパフォーマンスをやっていた表現者である津川さん。人間の内面性が現れる瞬間を捉え、それを表現者の立場で建築設計という形でアプローチしていくという建築家はなかなかいないのではないかと思います。
初対面でしたが、落ち着いた話し方で、津川さん自身の内面に惹き込まれました。
津川さんがつくっていく建築に心惹かれ、新たな表現者が自然発生していく。そんな渋谷公園通りの未来を想像しながらワクワクしてきました。
◾️津川恵理
ALTEMY株式会社 代表/建築家。ALTEMYは建築設計をはじめ、公共広場、ストリート実験、ランドスケープ、インスタレーションアート、テキスタイル開発などを手掛ける。人の感性に働きかける環境づくりを目指し、2019年に結成。
代表の津川恵理は、文化庁新進芸術家海外研修員としてDiller Scofidio +Renfro (NY)に勤め、神戸市主催神戸三宮駅前広場のコンペで最優秀賞受賞を機に帰国し、ALTEMYを設立。主なプロジェクトに『神戸市サンキタ広場』(2021)、『Spectra-Pass』@ポーラ美術館(2021)、『Incomplete Niwa Archives』@山口情報芸術センターYCAM(2021)、『タグコレ』展会場デザイン@角川武蔵野ミュージアム(2023)、まちの保育園 南青山(2024)など。
国土交通省都市景観大賞特別賞、土木学会デザイン賞優秀賞、東京藝術大学エメラルド賞、グッドデザイン賞、日本空間デザイン賞などを受賞。
ALTEMY公式HP https://www.alt-emy.com/