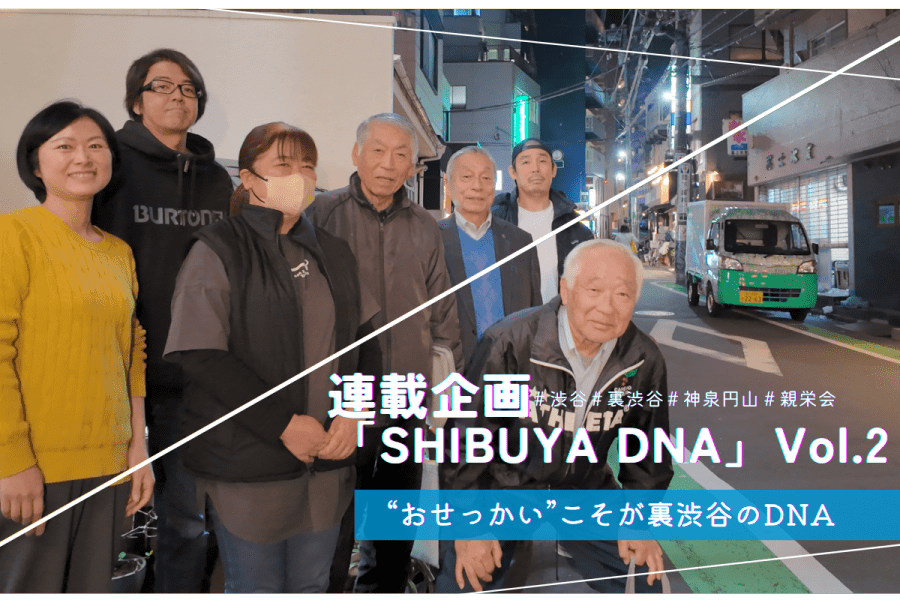Shibuya Sakura Stageではオープン時から桑沢デザイン研究所とのコラボで卒業生・在校生のみなさんが描いた絵や写真が様々な場所に展示されています。
前半では「Shibuya Sakura Stage賞」を受賞した吉崎亜希さんと「さくら賞」を受賞した柳沢葵さんにインタビューをしてきました。
後半は「髙谷賞」を受賞した福井一平さん、 ポラード碧さん、 丸山廉太郎さんの3人にインタビュー。さらに本プロジェクトにアートディレクターとして関わった桑沢デザイン研究所講師の髙谷廉先生から総評を頂きました。
髙谷先生から「髙谷賞」受賞者3人への総評
前編で吉崎さんが少しお話ししたんですけど、去年の広告の授業では課題テーマが2つあって、1つは硴とおばんざいのお店の「マルショウ アリク」のアウターブランディング。もう1つは、日本グラフィックデザイン協会の国際学生ポスターアワードにトライするというものでした。この2つの題材に対して、今回選ばせていただいたのは、「マルショウ アリク」を題材にした3作品です。
髙谷賞を受賞した3人はお店に通い、店主の廣岡さんとのコミュニケーションをかなり密にされてたんですね。人やお店、どういう人が集っているのか、廣岡さんがお客さんとどういう会話をしているのか、ということをよく観察していました。
福井さんの作品は2枚で1作品で、ポラードさんと丸山さんは1つずつです。
福井さんとポラードさんは写真作品です。福井さんの作品は少しザラついた質感で店主の日常を切り取っています。1960年代後半から70年代ぐらいに台頭したコンテンポラリーフォトグラフという文脈があるんですね。それこそ桑沢デザイン研究所を卒業した牛腸茂雄さんとかが代表的な作家で、文脈を汲んだ写真と感じました。
一方、ポラードさんは女性の視点で廣岡さんを捉えています。ソフトフォーカスで優しさが滲んでいながら、だけどモノクロの力強さもあって、コントラストとして非常に面白い。どちらの側面もそのお店は持っていると感じて選びました。
そして丸山さんはタイポグラフィ(文字や文章を要素としたデザイン)の作品です。手描きというアナログの手法をとっている点や、画角と造形の面白さ、ユニークさを評価しました。
髙谷賞 受賞者 福井一平さん
写真を撮るのはめちゃくちゃ好きです。始めたのは大学1年生くらいからで、最初はミラーレスで主に草花を写真に収めていました。それが3年ぐらい続いて、写真の歴史にも興味が出てきたんです。コンテンポラリーフォトグラフにプロヴォークというムーブメントがあって、森山大道さんとか中平卓馬さんの作品群に衝撃を受けました。それに影響されて今回のような感じの写真になったのかなと思います。
自分の中で事前情報はあまり持たずに「マルショウ アリク」に向かいました。はじめは、廣岡さんは堅い仕事人なのかなと思って、その作業中の風景を捉えました。でも、話をしてみると、廣岡さんは他人とのコミュニケーションがしたいという思いでお店をやってるんだと分かりました。なので、2枚目はそのエネルギッシュな側面を長時間露光で捉えた作品です。
構図は本などで学びました。デッサンもフリーター時代に少しやっていて、観察力がついたのかなと思います。写真もデッサンやデザインを始めてから上達したと感じました。
最近気づいたんですけど、僕、人撮るのあんまり得意じゃないなって。ありがたいことに今回は人物を写した写真を評価いただいて受賞に至ったのですが、主に建物、都市景観みたいなのをよく撮るんですよね。実は卒業制作でも都市景観の写真集を制作しました。
都市景観の写真が好きで撮っているのは、もしかしたら僕が東北や奈良で育って高いビルがない環境だったので、東京の高いビルに衝撃を受けたことが原体験として残っているからかもしれないです。田舎では時間が止まっているように感じることが多くて、それが窮屈に感じていたんです。だから都会の変わり続ける感覚が好きなんです。
写真っていうメディアが結構静的だから、見返した時にノスタルジックな感情が湧いてくることがありますよね。でも、僕はあまりそのノスタルジーが好きじゃなくて、昔は良かったみたいな後ろ向きになりたくない。都会は常に変わり続けている。それが好きで、写真を通じて表現したいと思っています。
髙谷賞 受賞者 ポラード碧さん
この写真を撮った日は、初めて「マルショウ アリク」に行った日でした。学校が終わってから22時過ぎにお店に行って撮影したんです。その時の印象を聞かれても、写真を撮るので精一杯だったので、あまり思い出せないんです(笑)
もともと全然写真を撮る習慣がなくて、初めてカメラを買ったのも桑沢に入ってからなんです。持っていたカメラも中古で買ったものでした。撮影は自然体でやりたかったので、被写体に決めポーズをさせたり、壁の前に立たせたりすることはしませんでした。
髙谷先生が「目に光が入っていないところがリアリティがあってユニークだ」と言ってくれました。普通のカメラマンは目に光を入れようとするんですが、私は全然そういうのを気にしなかったので、そこが新しい視点だったんですね。柔らかさが女性的で、モノクロだから力強さもあると言われたのが嬉しかったです。
モノクロで撮ろうと思った理由は、最初の写真の授業で先生がいろんな作品を見せてくれた中に、石元泰博さんの「シカゴ,シカゴ」という有名な写真集があり、それを見て感銘を受けたんです。とても貴重な写真集で、今では数が少なく、授業の時に先生が持ってきてくれました。「これカッコいいな」と思って、モノクロで撮ることにしました。
桑沢デザイン研究所に入った理由ですが、もともと高校でデザイン科にいたんですが、課題の量が嫌で逃げるようにして短大に行ったんです。でもコロナもあって、全然できることがなくて、このままじゃダメだと思って、親とも話して桑沢に入ることにしました。
短大ではデザインとは全然関係ないことをやっていたんですが、桑沢の課題の多さにびっくりしました。正直、また課題かよって思ったこともありました。でも、アウトプットの質が高まってきたと言われたのは嬉しいです。卒業制作もすごいって言ってもらえて、やって良かったなと思いました。
卒業してから今はあんまり創作活動はしてないんですけど、この春、松陰神社前に移転した「マルショウ アリク」の暖簾に描かれた硴(牡蠣)のイラストレーションを担当したんです。その絵を使って展示会を開く予定もあって、準備を進めているところです。
また店内で使われるサインも依頼されていて、江戸時代の大衆文化の一つである判じ絵をベースにしたイラストレーションにしようと考えています。これはお店の中でのコミュニケーションのフックになるようなものにしたいと思ってます。
今後の活動については、まだ具体的な計画はなくて、今はニート状態なんですけど(笑)。でも、これまでの創作活動やデザインの経験を生かして、もっと制作を続けていきたいですね。新しいプロジェクトにも積極的に取り組んでいきたいと思ってます。
やっぱり、デザインやアートに関わることはすごく楽しいし、これからも続けていきたいです。展示会とかサイン作りとか、今やってることをきっかけにして、もっと色々なことに挑戦していきたいですね。
髙谷賞 受賞者 丸山廉太郎さん
今回受賞した作品についてですが、アリクというお店の名前の由来を考えるところから始めました。アリクというのは、古語の「歩く」に由来していて、歩き回るという意味もあります。また、漢字で「在来」という言葉には、変わらずにあり続けるという意味が含まれています。このテーマを基にタイポグラフィ、文字での表現を考えました。
廣岡さんのInstagramを見ていると、ポストされていたものの中に大正や明治あたりの文字表現があり、それがとても魅力的だと感じました。そこで、大正や明治の文字をたくさん見て、その要素やエレメント、表現方法を掴もうとしました。アリクのロゴは普通にカタカナで「アリク」と表現されていますが、これを新しいバージョンで作ってみようと思いました。ロゴになるかどうかはわからないですが、一つの表現として作成したのが今回の作品です。
このロゴには丸みがありますが、線はどっしりとしていて、弱々しい線よりは太い線が合うと感じました。点の部分は硴の形をイメージしています。最初は全体を小さく作っていたのですが、髙谷先生のアドバイスで、A4用紙にもっと力強く表現するようにしました。
制作中、何度もアップデートを繰り返しました。例えば、文字の左右のバランスを見直したり、線の太さを調整したりしました。書道をやっていた影響もあり、余白やバランスには自然と気を使っていました。自分の中で文字を作ることが楽しくなってきたのも、その過程で感じたことです。
使用した紙についてもこだわりがあります。わら半紙を使いました。漂白されていない、ざらざらした紙の方がインクのにじみが良く出るからです。昔のイメージを出したかったので、真っ白ではなく少し濁った色の紙を選びました。紙の選び方一つでも、作品の印象は大きく変わったと思います。
アリクに初めて行った時のことを覚えています。最初は写真を撮りに行ったのですが、店主の廣岡さんとは他のイベントで会ったことがありました。話しかけづらい雰囲気がありましたが、実際に話してみると非常に話しやすい方でした。アリクの雰囲気も落ち着いていて、お客さん同士が自然と会話をするようなオープンな空間でした。廣岡さんの存在や店作りの考え方が、そのまま空間に反映されていると感じました。
受賞の連絡を受けた時は驚きと喜びがありました。この作品が選ばれたのは本当に嬉しかったです。アリクという言葉の持つ意味、変わらずにあり続けるというテーマが、渋谷という町のイメージともリンクしていると感じました。渋谷は常に変わり続ける町ですが、その中にある一貫したアイデンティティーも感じられます。私が作った文字の意味とも重なり、選ばれたことに大変満足しています。
これからの活動についてですが、まだ決まっていません。ただ、グラフィックデザイナーとして、自分の作ったものを見て依頼されるような仕事ができるのが目標であり理想です。簡単なことではないと思いますが、自分がなりたいその姿に向かって努力していきたいと思います。
前半の記事はこちら:Shibuya Sakura Stage×桑沢デザイン研究所 DESIGN WALL PROJECT受賞者インタビュー(前編) 吉崎亜希さん 柳沢葵さん