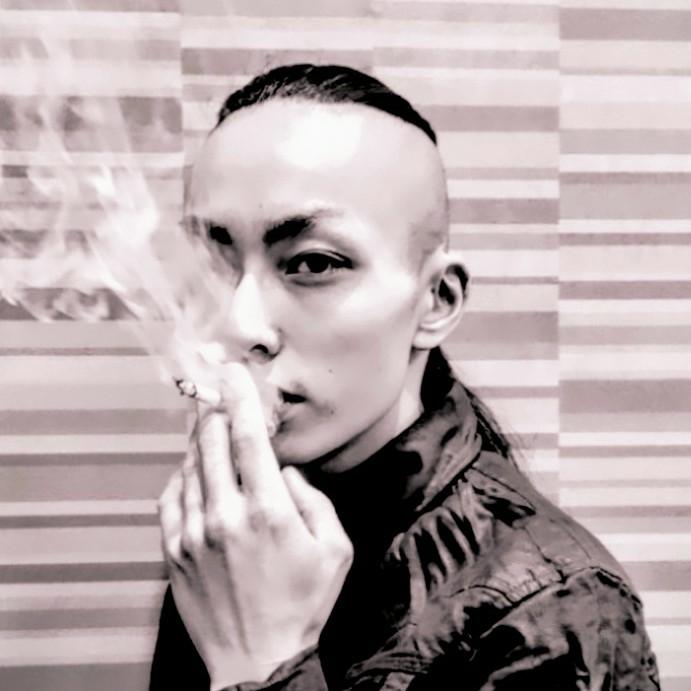若者に必要なのはきっと、暗中模索なしたたかさ。
僕はいつの間にやら、二十六歳。井上陽水は伝説的なアルバム『氷の世界』を二十五歳で発表しているし、とうとうアインシュタインが特殊相対性理論を発表した年齢になってしまった。が、どうやら僕は天才ではなかったらしい。
そして渋谷の青山学院高等部に通っていた尾崎豊が夭折したのもまた、二十六歳であった。約三十三年の歳月を越えて、同歳の叫びと甘美な響きに胸が震える。盗んだバイクで走り出したり学校の窓ガラス壊してまわったり、そうした反抗心や反骨精神は僕ら現代っ子には馴染みがない。だって今こんな事をしたら、ネットに実名と写真が晒されて一生が台無しになりそうだ。だから僕らは行儀よく、「物語の主人公みたいで格好いいな」といった感覚で聴いている。変わる世界の中でずっと変わらないもの、それこそがいつの時代にも新鮮に感じられるのだろう。いい歌やいい話はしっかりと時代を超えるもので、しかし世代によって感動の中身、感想は全く違うみたいだ。井上陽水も例に挙げると、『心もよう』は遠距離恋愛と手紙の寂しさを描いた素晴らしい曲。
「黒いインクがきれいでしょう 青い便箋が悲しいでしょう」
という歌詞も、僕にとってはファンタジー作品に触れるような感覚。手紙なんてほぼ書いたことがないし、今はスマホで繋がれる時代。卒業式だってみんな泣いてなかった。
このように、現代ではデジタル技術によって、世代間ギャップはとてつもなく大きく開いている。見えるものは一緒でも、世代によって見えているものは全然違う。時代の変遷というものに寂しさを覚える方は、きっと多いことだろう。
そんな、世代についての話題を持ち出そうと思ったのは渋谷/原宿表参道新聞の編集会議の様子から。中学生のメンバーがいたり大学生が進行を担ったり、70年代に青春を送った方が助言や冗談を言ったりする。立場も役職も年齢も、何もかもがごちゃまぜで賑やかな空間だ。いかにも渋谷らしい、とても新鮮な環境だった。そうした「世代や立場を超えて交流できる環境」が身近にある方には、その当たり前の素晴らしさをもっと知ってほしい。そしてコミュニケーションで寂しさや困難を感じている方は、ぜひ一緒に考えて欲しい。今回はそんなことを思って、ちょっと変わった世代論のお話をしよう。
まず世代間ギャップにおいて、僕ら若者に足りていないのは上の世代との会話なんじゃないか? と仮説を立てた。地方から上京して渋谷区内に就職して、そこでようやく僕は「外部の大人との会話」を経験した。これは決して大げさな話ではなく、田舎町では親か先生以外の大人と話す機会なんて、本当に今まで無かったのだ。若者言葉で言えば「コミュ障」と言いくるめられる状態だけれど、問題はそう簡単ではない。ネット環境による繋がりの増加で、コミュニケーションは充実ではなくむしろ形骸化している。それを僕は身をもって実感していて、上の世代の方が若者に思う事も実際かなり的を得ている。
例えば前回のVol.02で僕は、甘いものと散歩と読書について綴った。それでなんとなく、現代的な落ち着いた若者を想像されたかもしれない。そもそも普段の生活では、僕が小説やエッセイを書くとすら伝えていない人がほとんど。同世代の方たちもきっと、表に出していない趣味や感情を幾分もお持ちだろう。「落ち着いた現代っ子」だけが若者の全てではないことを、話さなければ伝わらないし良い関係も広がらない。現代の若者は特に、自分の趣味や特技をあまり話さない人が多いと思う。否定や期待が怖いとか、面倒くさいとか、リアルなら冗談で済むのにネットだと炎上するだとか、そんな現代流SNSの処世術は常々、現実にも持ち込まれている。そうした、若者が怖がって出せない自分というものを、もっと表に出していける風通しのいい社会であってほしい。これは若者だけの問題でもなく、上の世代だけの責任でもない。ではどうすべきかと悩んでも、そんな簡単に答えは出ないものだ。
そこで、もっと「若者の社会観」を深掘りするために一旦社会から離れてみよう。それからもう一度渋谷を見つめ直して、「若者っぽさとは?」をイチから探ってみよう。
さて、文通の例えにもある通り、僕は初期の「デジタルネイティブ世代」だ。世間的には他にも「Z世代」「さとり世代」「脱ゆとり世代」などといったレッテルが貼られている。最近の若者には覇気や夢がないとか、ネットやゲームばかりで趣味がないとか、そういうレッテルを貼りたくもなるらしい。誰が貼って誰が拡散しているのかも、匿名化の進んだ社会ではよくわからない。人は誰しも完璧にはわかり合えないし、自分のことだってよくわからない。まあそれは当然のことだけれど、やはり若者にとってみても、年齢の離れた方とのコミュニケーションはなかなか難しいものだ。編集会議などで様々な世代と話したこと、そして普段の仕事や生活で感じること、あるいは社会そのものから離れて山の上で気づいたことなど、今回はあちこち暗中模索に飛び回ってみよう。
僕は時々、山に登る。生きるために必要なすべてを背負って文明の外をゆく、そんな大昔から存在する趣味だ。二泊三日で北アルプスなどに登って生きて帰るには、荷物はグラム単位で軽い方がいい。普段必要なものをほぼ全て置き去りにして、命の不可欠条件のみを迫られるわけだ。最後に残るのは三日分の水と食料、カッパ、防寒着、テント、救急キットなど、なんとか15キログラム程度まで絞る。それでも米袋を三つ持って一日中階段を登るような、そんなイメージだ。山の中では水も食べ物も電気もないし、スマホは圏外。普段当たり前にあるすべてから見放される。背負っているもの、脚と精神力、そして理性だけが頼り。
そんな孤独な時間を過ごしていると、時には心が苦しくもなる。山なんか登って何の意味があるんだとか、無駄で疲れてお金もかかって危険で、もう絶対二度と登るもんかとか、何度でも毎回思う。
「なんてちっぽけな、なんて意味のない、なんて無力な」
という尾崎豊の歌詞がぴったりだ。どれだけ普段恵まれて助けられているちっぽけな生き物なのかが、山に登るとよく分かる。すべての経験に何かの意味はきっとあるはずで、何にできるかは自分次第。今いる場所から逃げたくとも、結局来た道を歩くしかない。だからこれは “なんたってやるしかないこと” だ。そう言い聞かせて一歩踏み出す脚の痛みや自然の雄大さが、己の弱さを強く教えてくれる。そしてじわじわと、尾崎豊の感覚が分かるような気がしてくる。
下界じゃ歳上の人とは話が合わないし、自分の価値なんて知らないし、この社会を生きることは非常に面倒で、辛いことのほうがずっと多い。はっきり言って嫌なことばっかだ。ほぼすべては社会が悪いんだ……とか思った直後には、そうやって自己憐憫に甘えて逃げている自分が嫌でたまらない。未熟な若者の僕はちょうどデジタル信号みたいに、善悪や責任なども0か1で考えてしまう。そのくせ、じゃあ生きたいか死にたいか、そうゼロイチを問われても即答できない。生きる強さも死ぬ勇気も無い。生きても迷惑をかけるし、死んでも迷惑をかける。両極端な0と1の間にあるアナログな不安の振れ幅に、胸がぐっと苦しくなる。これでいいのか、どうしたらいいのか……と、曖昧で矛盾だらけの自分を受け入れられないまま。ただ目を逸らして、身近な娯楽でぼやかしたくなる。
そうこれだ、これはきっと、かなりさとり世代らしい感情だ。誰だって生きていれば、消えてしまいたい日もある。それは決して悪いことではなく、死にたくなるほどに生きている証拠。そんな0と1しか無い粗い目盛りの間に、細かい小数点や奥行き、別のものさしを増やしていけるもの。それが上の世代の経験や知識ではないだろうか。田舎の複雑な家庭で育った僕にとってはそれが本で、芥川龍之介などの作家たちだった。遥かに上の世代だ。子供の頃は頼れる大人を見つけられず、ひたすらに文字を追った。だから世代間の楽しい会話を見ると羨ましく、とてもあたたかい気分になる。親子の楽しげな会話、上司と部下の気心知れた雑談、学生であれば相談できる教授など、そうした繋がりはあまりに尊く、特別なもの。僕を何度も救ってくれた芥川龍之介も堀辰雄も森鴎外もカフカも、大事なときに限って答えをくれない。読書中に自分を見つめているのは本でも作者でもなく、自分自身だ。
「じゃあさとり世代って、結局なにを悟ってるんだろう。この感情はなんだろう。何を信じればいいんだろう。虚しさみたいなものを感じられるということは、まだ僕は虚しくないはずじゃないか。どうしたらいいんだろう、こんなの誰も教えてくれなかった。なぜか脚は一歩一歩前に進んでいる……」
なんて感覚を胸にしたまま、先日は登山未経験の友達を誘って低山に登った。こうした想いを同い年と共有したら、何かが分かる気がしたから。その山頂で撮ってもらったのが今回の写真だ。そして登りながら話をして、
「さとり世代とは、贅沢と幸福の違いを悟ってしまった世代なんじゃないか」
という考えが、あえて不便や苦難を選ぶ趣味を通して浮かんできた。というのもかつて、テレビ、洗濯機、冷蔵庫を三種の神器と呼んだ時代があった。あるいは結婚やマイホームやマイカーがステータスで、大多数が似たような夢を追った時代があった。アメリカンドリームに似た贅沢至上主義の時代では、富と贅沢と幸福はほぼ同義だったのだと思う。それに対して現代の若者は、幼い頃にインターネットという “知恵の実” をかじってしまった。今はオンラインゲームや動画サービスなど、安価に得られる楽しさがたくさんある。だからわざわざ挑戦やリスクを冒して富を求めるよりも、ただフリーな時間のほうを選びたいと思うのだ。あるいはここ数十年で急速に便利で贅沢な世の中になっているはずなのに、幸福度は比例しないことにみんな気づいた。様々な世界を画面越しに見て育ち、嫌な現実も知りすぎてしまった。かつては尾崎豊のような盲目な「不満」だった若者の心が、今では情報過多による「不安」に置き換わったのかもしれない。不満は人を歩かせ、不安は立ち止まらせるものだ。
人類は20万年以上続いてきた「目に見えない人と人の繋がり」そのものを、正にこの時代を転機にテクノロジーで制御するようになった。これはもう、二つ目の禁断の果実と言っていいんじゃないかと思う。本当に大きな転換期に僕らは生まれた。この大量生産された食べかけのリンゴを、私たちは今さら手放せない。スマホは単なるデバイスやツールを超えて、今や個人と社会に複雑に絡み合っている「構造」そのものだ。だからデジタルネイティブ世代に生まれた僕らは、そこに強みってやつを見出さなきゃならない。
ちなみに、あのかじりかけのリンゴのロゴには、聖書にある禁断の果実なんて意図はもちろん無い。最初の製品である「Apple1」は1976年の発売で、同社が世界を変える時代が来るとは誰も思わなかった。ネットやパソコンが普及するよりずっと前、一見すると電卓の中身のようなものだ。画面もキーボードも付属せず、剥き出しの基盤一枚にトランジスタが並ぶ、一般人には全く理解できない製品。そのApple1を一億台ほど並べたら、ようやくあなたのスマホの演算速度に追いつけるかどうか。それほどにコンピュータやインターネットの進化は凄まじい。一人一台オンライン端末がないと何もできないほどのIT革命を起こした現代なんて、当時は誰も想像できなかっただろう。そのとてつもない構造がもう、僕ら世代の小学生頃には「一家に一台」を飛び越して一人一台になっていた。あって当たり前で、誰も手放せないもの。かつてこんな短期間で人類に浸透したこのような「新常識」が他にあっただろうか。そんな禁断の果実を人造したことを、私たちはだいぶあとになってから理解した。まるでSFみたいな世界だ。だから僕は、ネット環境が無かった時代をどうしても想像しきれない。電波の届かない山登りに自分を放り込んでようやく、社会との繋がりを遮断できる。やっと自分自身をしっかり感じられるような感覚がわかる。そんないかにも生き物らしい心に会いたくて、僕は大自然の山を目指すんだと思う。「広い視野で悟った気になって、実は何もわかってないんだぞ」と、自然は教えてくれる。日本の国土の30%以上が常に圏外で、また国土の約70%は森林。全てに恵まれた東京に暮らしていると、思いもよらない事実だ。
ここでひとつ、実際に見て感じることだけが全ての世界というものを想像してみてほしい。そう言われても何のことやら、パッと想像できないくらいに周囲はデジタルで溢れている。
例えば北アルプスを二泊三日かけて登ってやっと見られる雄大な自然がそうだ。すべてが報われるほどに美しい。ああよかった、僕は僕としてここにいる。生きてる。そう思うくらい、デジタルネイティブ世代にとってのネイチャーワンダフルは特別なものだと思う。自分が透き通って感じるほどのすがすがしさを、身近なものに例えるならなんだろう。真夏コンビニに入った瞬間の感じ、スイカと風鈴の雰囲気、銭湯の牛乳、仕事終わりのキンキンのビール、あるいは夜中や日の出前に静まり返っている街の空気。山の風はそんな感覚に少しずつ似ている。アナログでリアルな、“エモい” 感じだ。この若者言葉はデジタルネイティブ世代だからこその、現実の再発見なのだと思う。現代版「わびさび」と言ってもいいかもしれない。ネットに深く関わってこそ分かる現実の良さというのもまた、結構あるものだ。
山の上の星空は、非常口も解説員もないプラネタリウムだった
圏外で人ひとり見当たらず、山奥にひとりぼっち。日はもう落ちかけている。そこでは富も名誉も役に立たない。そんな山の中腹にテントを張って、質素な保存食と少しの水を補給したあとの話をしよう。寝袋でしばらく休んでから、僕は必ず深夜に一度目覚ましをつけておく。当然電灯なんかひとつもないのに、新月の星明りだけでしっかりと歩むべき道が見える。そんな場所の夜空の話だ。そこでは自然と渋谷双方の素晴らしさが言葉を超えて伝わってくる。岩だらけで全く人工物のない場所から見る宇宙は、本当に虹色だ。視界の隅から隅まで、宇宙が本当に七色に輝いている。そう、山の星空はマジ綺麗でめっちゃエモい。その景色を大昔の日本人は「ふたりをつなぐもの」と考えたらしい。アルタイルを彦星、ベガを織姫と名付けて、筋のようにつながる絆を天の川と呼ぶ。遠く離れた恋人と文通もできず、たったひとつの繋がりがなんて淡く、儚いのだろう。江戸時代や戦時灯火管制下の渋谷では、どんな美しい星空が広がっていたんだろう。そんなぼんやりとした七色の模様を眺めていると、少しずつ点の集まりが見えてくる。空と宇宙の境い目なんてなくって、自他の境い目さえ闇と光にほどけてしまう。自分というものを強く感じるのに、同時に体がサラサラと消えていくような不思議な感覚だ。音も匂いもライトもなく、目と感覚だけが宇宙に浮いている気分になる。あまりに空が広すぎて寒いような怖さも感じるけれど、「降り注ぐような星空」なんて表現はこんな感覚から生まれたんだと、しみじみ思う。贅沢さを削ぎ落としたはずの登山は、なぜかとても贅沢で幸福な時間をくれる。
そして次の日また尾崎豊メンタルで歩き続けて帰る頃には、嫌だったはずの日常や煩わしさがとても恋しくなっている。ハンバーガーが食べたい、ケーキが食べたい、清潔な服を着たい。そのためには、面倒に感じるすべての事柄が必要だ。そうかそうか、面倒な事はみな、僕を社会につなぎとめるためのものだったらしい。そんな気づきと共に渋谷に戻れば、人間は江戸の星空を東京のネオンに変えたことを思い出す。都市部では利便性と引き換えに天の川は見られなくなった。夏の大三角はかろうじて見えるけれど、その中にあるはずの天の川星雲は全く見えない。でもアパートのベランダから色のない夜空を見ても、全然さみしいとか悲しいとは思わなかった。きらびやかな夜景は様々な色に輝いて、遠く離れた恋人ともいつでも話せるような環境だ。お金さえあれば食べたいものを食べたいだけ食べられるし、スマホひとつで人と繋がれる。そんな都心はまるで天の川にいるみたいにきれいで、天界が地上に降りてきたようなぬくもりを感じる。ああ、ベッドがこんなにも素晴らしいものだったとは。ファストフードがこんなにおいしかったとは。身の回り全てがありがたい。贅沢で、幸福だ。
そう思ってもほんの数日も経てば、不思議なことに僕は都会の現代っ子に戻っている。あっという間に社会の不安でいっぱいになっている。これが一番衝撃的だった。当たり前にある贅沢は、思う以上に人を盲目にしてしまう。すぐに幸福を忘れる。あなたも息を吸うことなどは当たり前すぎて、わざわざ空気に感動などしないだろう。日ごろ自分を守ってくれている「当たり前」への感謝を、私たちは忘れ続けて生きている。僕も日ごろ深く考えているつもりで、エコーチェンバーやフィルターバブルなんて呼ばれるものに閉じ込められているらしい。本当に、自分の盲目さと色眼鏡に若いうちから気づけてよかった。「最近の若者は覇気がない、主張がない」と思われてしまうのも、確かにその通り。だって何をどう思えばいいのか、どう話していいか、あまりに情報が多くて見当もつかない。いつも他人の意見や情報でいっぱいだ。それで結局ネット上で愚痴や独り言を呟いて、似た者同士承認しあって褒めあって満足して、リアルでは愛想笑いばかり。そんな感覚は、現代の若者のよくあるコンプレックスとして扱われている。でもそれを自分自身のせいだと結論づけてしまうのが怖いから、同世代の友達などからはこんな話が出てくるものだ。
「なんでどうでもいい昭和の話を聞かされて大げさに驚いて顔色伺わなきゃいけないんだ。こんなに歳が離れてるのに話なんか通じるわけないじゃないか」
と、そんなふうに考える若者は今後も増え続けるのだろう。若者から積極的にコミュニケーションをとれば収まる話なのに、それがなかなか難しい。これは趣味やネットサービスの中だけで狭いコミュニティが完結して、他人との雑談がめっぽう減った結果だ。最近は若くして起業する人やベンチャー企業なども増え、少子化だって言い換えれば少数精鋭。若者の未熟だからこそ新鮮な視点や疑問、そして中高年者の豊富な経験と知識に基づいた潤沢な主観、その世代間の違いがうまく交われば、きっと素晴らしい力になるはず。そこに付ける目標の名前はノーマライゼーションかバリアフリーか、何が合うのかよく分からない。横文字を並べてもいまいちピンとこない。
そんな、振り出しとはるか遠くを行ったり来たりして考えるうち、僕が世代間ギャップについてとてもさみしく思ったことを紹介しよう。
「最近の若者は」とおっしゃる世代も、産んでここまで育てて下さった世代も、あまり変わらないではないか。
「ネットやゲームに夢を見て過ごしている」
「最近の若者は落ち着きすぎ」
「痛みやストレスに弱い。すぐに泣く」
「いい時代、だった」
そんな言葉たちが、ネットで瞬く間に拡散され、あるいは会社内や接客の現場でふと言われ、でも若者にはどうしようもない。だってネットやゲーム、加工食品、ストレス耐性がつかない恵まれた環境などは、上の世代が創り上げてくれた安寧。それらを譲受側の若者への批判に使うのは、どうか避けてほしい。選べない生まれや育ちを批判されるのはとても悲しいことだし、大多数の若者は「生まれたのが現代でよかった」と思えている。だからもっと、未来の話をしよう。僕ら若者はいずれ次の中年層として、社会を支えていくことになるのだから。その時までどうか、中高年層の方々は希望を絶やさずそばにいてほしい。チャレンジ精神や夢を描く方法、描いてもいいと思える安心感、ネガティブな側面から入らない方法、それをどうかたくさん若者に受け継いでいってほしい。そして若いみなさんは、逃避行でも盲目でもない希望の形を、これから探していかなきゃならない。過去を自分や誰かのせいにして終わりではなく、未来へ向けてできることを探し続けよう。そんな気持ちを込めて、今回は「したたかさ」という言葉を使った。色んな意味を持つ言葉だから、よければ一度意味を調べてみてほしい。ああ、こういう時AIを活用するのも面白いかもしれない。今回うまく分からなかった部分、あるいは全文をそのまま言語生成AIにコピペして、分析や議論をしたらどうだろう。
その結果が「この文章は駄作です」「これはAI生成です」みたいな返答じゃないことを祈りたい。僕はもちろん執筆にAIは使わず、たとえ過ちがあろうとも自分自身を出すことに専念している。だから書き手の僕が次にすべきことは、なんとか勇気を出して上の世代にお話を聞くってこと。
「世代間ギャップ」について、親世代の方にお話を伺った
「問題とか悪いところってのは、簡単に思いつける。無限に作れちゃう。ネットにもいくらでも溢れてる。悪いこと嫌なこと考えずに本能に抗って何かやるって、やっぱりすごく難しい。けどそれが非常に重要なことなんだよ。人間は怖がったり嫌がったり、ダメなところを見つけたり、そういうのは本能的に当たり前のこと。でも野生と違ってこれだけ整った社会、やたらめったら怯える必要ないんだしさ、ネガティブじゃ社会はうまくいかない。良い目標を立ててちゃんと書くとか、日記を習慣にするとか、そうやって本能に抗わなきゃ。だから人生は習慣がほぼほぼ決めるって、僕は思ってるよ」
僕の「0と1の間のアナログな不安」に対してそう教えて下さったのは、渋谷新聞アドバイザーの一人である 角田朋哉 さん。メンバーのみんなはつんつんさんとお呼びしている。ちょうど僕の親くらいの世代で、そんな方が笑顔で希望の形を話してくださるのはとても頼もしく、ありがたかった。朗らかな中にちくりと厳しさが光り、自ずと気づかせてくれる。景色の見え方が変わる。まさしく人生の先輩だと思った。もちろん大人の言う事は常に従おうだとか、これこそが正解だなんて言うわけではない。でも勇気を出して中高年層の方に話しかけることで、一気に広がる発見や解決可能性がたくさんあることは確かだ。僕も日記はよく書くけれど、それが「習慣」だってことにすら気づいていなかった。
そこで自分の日記を見返してみると、つんつんさんの言葉に頷きが止まらない。不安や不平から解決策を探って「これはこう正すべきだ。ここがダメだ」って不満の結果にしたがるクセであふれている。いかにもさとり世代らしいなと思った。僕なりの正しさは他人にも、そして僕自身にも、決して押し付けてはいけないと気づけた。僕もあなたもすべての人も、びっくりするくらい間違え続ける生き物だ。だからこそ人は未来永劫、伝え合い支え合い認め合わなきゃ生きていけない。関わりを絶ったら山岳遭難も同然。とするともしかしたら、読んで下さる方以上に、書いている僕自身が一番学ばされているのかもしれない。こうした執筆もひとつ、僕なりの脱ネガティブの一歩。無理してポジティブ思考や笑顔を演じてもきっと、上滑りしていい変化は訪れない。それは習慣ではなくその場しのぎだ。変化というのは必ず心が怖がってしまうもので、日々の中に小さな目標やチャレンジ精神をまいていけば、気づいた時には変化は咲いている。それが習慣と言うのだろう。なるほど、「人生は習慣が決める」とは全くそのとおりだ。
己に対してそうやって厳しく優しく接するのが、恐らくコスパもタイパも一番いい。それで空いた時間で、考えたり話したり、本を読んだり散歩をしたり、人間らしいことをしよう。これは前回のVol.02からつながるテーマ。と言いつつ僕はまだまだ、夜更かしのネットが楽しくてやめられない。まだ買って積んである本がいっぱいあるのに、なかなか進まない。まずは一冊と言わず数ページ、少しずつ、始めてみよう。
さて、結局のところ一体何が正しいべきなのか、何を信じるべきか。それは言い逃れや弱腰でもなく、次の世代へと永遠に問い継がれていくものだと思う。私たちは弱いから、壊れない強固な正解をいつも求めてしまうもの。でも本当はこの世に正解なんてない、僕もわかってはいた。それを受け入れる柔軟さは、二十六歳になってもなかなか身につかない。常識も理想も普遍ではなく、常に移ろう諸行無常。一切皆苦の諸法無我を生きるしかないのだ。大切なことはひとつ、見つからないと知りながらも、正しさを探して歩き続けること。
“見ている景色 見えている景色” 、これは「ものは言いよう」なんて言葉で言い包められる意味の比喩だ。けれど、言いようによってものの見え方や考え方までも変わるなんて、とても素敵なことじゃないだろうか。そしてデジタル時代にはもう一つ、 “見る景色” 。情報過多の現代で何を見て何を見ないかもまた、あなた次第。暗いニュースをどれだけ集めても、何も明るくはならない。その単純で難しい「多様で明るい視点」を、一生探していこう。僕の執筆はその連載名の通り、それだけ伝わってくれたら充分かもしれない。
……そんな話をここまで書いて、まとめに入る予定だった。渋谷新聞副代表の鏡晋吾さんに「できました」と確認をお願いしたところ、出てくる出てくる、上の世代の引き出し。もう少しだけお付き合い、よろしく。
「へぇー今の若い人でも尾崎豊わかるんですね。ちょうど高校生の頃に大ヒットしてたんですよ。僕の親世代は学生運動なんかが盛んだった時代だからそういう反抗心はまだまだ身近で、尾崎豊もみんなの憧れでした。今の若者はどんな感覚で聴いているんだろう。やっぱり僕の世代とは違うんだろうなぁ。ああそう言えば、渋谷クロスタワーのところに記念碑あるじゃないですか」
相槌を打ちながらお聞きしていると、おっと記念碑? なんだそれは。ネットはそんなの教えてくれなかったぞ……なんて思って検索すれば、確かにすぐ出てくる。僕の調べものが足りなかった。人とのつながり、上の世代の知識や経験、恐るべしである。この記念碑については渋谷新聞の運営の記事でも書かれていたので、ぜひこちらも読んでみて欲しい。僕が尾崎豊を取り上げたのは全くの偶然だった。ネットはつくづく、「知ってることしか調べられない」ものだ。
参考記事:尾崎豊が過ごした街 渋谷 Vol.1 –
お話に出た学生運動とは、そんなに前だったのか。三島由紀夫が東大全共闘と討論した動画はとても面白かったし、69年の東大安田講堂事件は「若者の覇気」の極致みたいに見える。ひどく愚かしいと思いつつ、でもその熱意は尊いと思うし、いかにも若者らしくてどこか格好いいとも思う。どちらにせよ物語みたいな感覚だ。現代では若者の政治離れが嘆かれ投票率も低く、きっと二度と起きない類の事件。それがいいことなのか寂しいことなのか、人によって全く意見は違うんだろう。あなたはあの頃の若者と今の若者について、どんなことを思い浮かべるだろうか。なんにせよ投票は、特に若い世代の人はみんな行こうね。若者の投票率が上がるって事は、将来のためにとても大切なことだから。社会を離れて生きていけるほど、人は強くない。
やっと、まとめ
登山みたいに長い文章になってしまった。どうだろう、長すぎただろうか。
前回までの連載でも、僕はあえてそのまま残している不足がいくつもある。微妙な矛盾や曖昧さ、難しい単語、格言っぽい言葉遊び、曲名など。それらを細かく説明しないのは、「次に繋がり続ける一歩目のアクション」を起こしてもらえると嬉しいから。一回読んで全てが理解できる人なんて居ないはずだし、……と言いつつ、本当に僕が間違えている可能性もある。だから読んで下さったあなたが「これはなんだろう」「ここ間違いじゃないだろうか」ってネットで調べたり自由に考えたり誰かと話したりして、あなただけの好きな想いを作ってほしい。人は誰だって、生きているなら間違い続ける。それは間違いない。あなたもたくさんミスして迷惑かけて、いっぱい叱られていっぱい謝って、悩んで困って逃げて、何度でもチャレンジし続ければいい。
ミスは経験の失敗ではなく、失敗の経験。いつか絶対に、自分や誰かの役に立つ。失敗を助けてくれた人へ申し訳なさと感謝を強く感じて、あたたかさを噛み締めよう。そしていつか自分にできる手助けが見つかったら、全力で助けてあげよう。他人のミスを怒らず、「困ったときはお互い様」って笑い合える環境、そんな場所なら世代間ギャップも認め合えるはず。そう考えると〇〇世代といった呼び名も、おおよその特性を理解するためには便利なものさしだ。でも絶対に、それを批判の道具に使わないこと。
今回の課題として扱った世代間の交流は、地味で小さな、形のない姿勢について。そして具体的な行動として、我々は「まなぶや」「渋谷区SDGs協会」などの活動を行っている。大人から若者へ、あるいは子どもから子どもへ、「同じ空間で伝えあう」ことの大切さを、これからも大切にしていきたい。
誰かと自分をどうしても比べたくなってしまう時は、間違いと苦い経験の豊富さで競えばいい。僕もあなたも失敗していい。いや失敗するべきだ。転ばなきゃ、立ち上がれない。人間って、人生ってそういうものじゃないかな。
そんなわけで、暗中模索にあちこち飛ぶ忙しいお話もこれにて終わり。読んでくれてありがとう。次は何を書こうか。リクエストやご感想、お叱りなどぜひぜひ、コメントをお寄せ下されば幸甚。ではまた、次回。
おまけコラム プラネタリウムと渋谷の深いかかわり
2001年まで、東急文化会館に五島プラネタリウムがあった。今は渋谷ヒカリエのある場所だ。当時使われていたカールツァイスⅣ型プラネタリウム投影設備は今、「渋谷区文化総合センター大和田」の2階ロビーに展示されている。渋谷駅前の発展の象徴とも言える東急文化会館、そしてそこで輝いていた西ドイツの名機もぜひ、「五島プラネタリウム」をネットで調べてから見に行ってほしい。戦前戦中の渋谷のできごと、そして戦後渋谷の発展について、たくさんいろんな知識が増えるはず。また文化センター12階では現在、コニカミノルタのジェミニスターIIIプラネタリウムが稼働している。僕が北アルプスで見た星空の感動が、きっとあなたにも充分伝わる。若い人はセンター12階の「コスモプラネタリウム渋谷」で、東急文化会館に思い入れのある方は2階ロビーで、それぞれの想いや世代論を互いに語り合ってはいかがだろう……