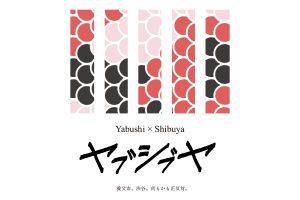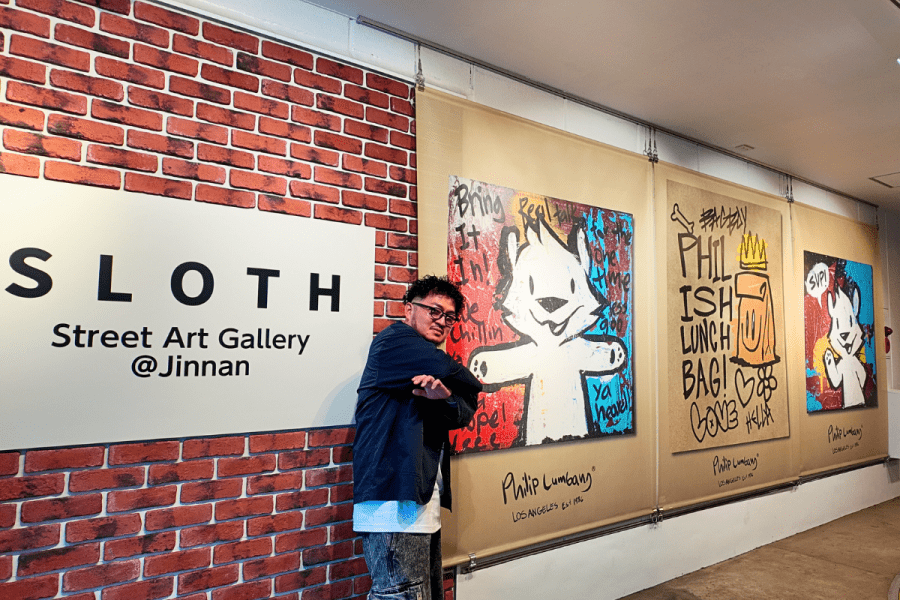6月28日から渋谷シネクイントで2週間限定上映されている、「そうして私たちはプールに金魚を、」「蟹から生まれたピスコの恋」の脚本家・監督である長久允(ながひさまこと)さん。学生映画から一度は挫折を味わい、様々な経験をした長久監督だからこそ持つ感覚で描かれた作品について、お話しいただきました。
渋谷との繋がり
ーー今回、「そうして私たちはプールに金魚を、」「蟹から生まれたピスコの恋」を渋谷シネクイントで上映することになったきっかけを教えてください。
「そうして私たちはプールに金魚を、」は7年前、「蟹から生まれたピスコの恋」は 去年製作したもので、今年のサンダンス映画祭で監督賞をいただいた作品なんです。どっちも短編映画なのでなかなか上映には回らないんです。ただ、映画館で観ると音が感情とダイレクトに繋がって、スマホとかで観るのと全然違う感情になると思っています。
そして、「蟹から生まれたピスコの恋」は今配信にもどこにも置かれてない、誰も見れない状態なんです。それはもったいないし、たくさんの人に観てもらいたいなって思いがありました。それで今年の1月くらいにX(旧Twitter)で「2本立て上映、映画館経営の皆さんいかがでしょうか」みたいなポストをさせてもらったら、渋谷シネクイントさんからご連絡いただいて、上映にやっとこぎつけたという経緯です。
ーー監督自身、渋谷はよく来られるんですか?
僕は青学出身で、大学生時代はずっと渋谷にいました。
僕が大学生の頃は今の倍くらいシアターがあって、いっぱい行ったんですけど、シネクイントさんで言うと「バッファロー’66」とかは見たかな。他にも色々邦画を見たり、学生の時からよく通った映画館です。 あと「ウィーアーリトルゾンビーズ」とか、僕の作品もいくつかかけていただいたりしてるご縁もあるから、ホームの劇場で上映できるっていうことはすごい嬉しいですね。
今でも、脚本に行き詰まったら渋谷を歩くことがあります。誰も他者のことを見ていないという、渋谷ならではの空気感が心地良いです。

命をかけて、作り上げる作品
ーー今の若者は、共感や繋がりを強く求める傾向にあると感じています。その中で長久監督の作品は、他人に共感しない、合わせないキャラクターが多いと感じました。その点で意識されていることはありますか?
日常の話で言うと、本当は監督としてはヒットさせないといけないから共感を考えないといけないんですけど、僕自身そういうのがなくて。この時代だからこそ、僕はSNSの投稿でいいね1が本当に嬉しい。みんなの公開の場だけどこの人1人とは繋がってる、みたいな感じがむしろ興奮する。バズりたくないというか。バズることなんかより、いいね1、2ぐらいの、その人ぐらいにしかわかんないポエティックなゾーンのことに、わかるわかる〜ってやってる方が繋がりを感じて、アツいなって思ってて。だから、僕のXは宣伝かポエティックなことになっちゃってるんですけど、僕はそれが一番いいなと思ってます。
結局、共感を目指すと言っても無理することになるので。僕自身なんで作品を作ってるかというと、自分がそうだったからですけど、30人のクラスの1人、隅っこにいる1人しかわからない感情のために作っているところがあります。そういう目的で映画を作ると、みんながわかるエモーショナルな共感っていうよりも、すごい細かい感情を自分を信じて作るしかないかなという思いがあって。多分こういう人間が自分に嘘なく作ると、登場人物もみんなドライな感じになっていっちゃう。カーストの外にいるというか、下にいるというか、そういう人たちのために作ってたりもします。や、本当はカーストなんて存在しないんだけど。自分もそうだから、そういう人たちがプロットされていくんだと思います。
基本的に、人間は1人。あとは他人。でも、 人と人とはジェントルにあらねばならならない。親切にあらねばなと思っています。そこでは、嘘みたいな愛情やフレンドシップはまやかしになるかもしれない。でも、人と人とはお互い切度を持ち、モラルを持ち、ジェントルであらねばならないっていうのはすごい僕が人生で思っていることで。 個人個人を尊重していくみたいな、ある種その冷たさは大事にしていくっていうことを思ってるのを、脚本にそのまま入れてる。 それこそが愛と言われるものかもわからないですけど、ピスコとくぼかよの関係性ってのはお互いをいい距離で肯定してくみたいなことで、理想的に見えます。でも、基本的には孤独であるってことはベースとしては思ってます。結局は分かち合えないし、全員身勝手である。でも、それでいいんじゃない。ちょっと息があったら良いよね、カラオケで盛り上がったらいいよねっていう。 その瞬間が一番幸せなことかもしれないよねっていう。全ては孤独で虚無だけど、一瞬カラオケで盛り上がったら最高! っていうことを思ってます。
ーー伝えたい人に伝わることって大事ですよね。
僕は「そうして私たちはプールに金魚を、」を作ってから色々な賞に出したけど、国内の賞はほとんど引っかからず、その中でサンダンス映画祭は見つけてくれました。海外の映画祭って、迎合をしてるものよりもオリジナリティーのある感覚や表現をちゃんと冷静に見つけてくれるから、サンダンス映画祭があって本当に良かったなって思います。迎合したもの作ったら、逆にサンダンス映画祭は弾いてたと思うから感謝してます。賞があるとね、人が観てくれるから大事ではあります。1パーセントにしか伝わらなくても、1億人の1パーセントは多いから。
ーー賞を取ってから、多くの人からの支持を受けるからこそのプレッシャーとかありますか?
売れなきゃ次の映画にお金がつかないんで、売れなきゃなという思いは強くあります。でも単純に作るのが、本当に脚本書くのが超好きなんで! 作るのが好きだから仕事が楽しいし、あんまり強張ってないです。いつか無邪気にでっかい「グレムリン」とか「ジュラシックパーク」みたいなのを楽しく作りたいです。比較的無邪気にたくさん作りたいって感じ。毎回作るごとに死ぬ気でやる、全部その時に自分が正しくないと思うことは入れないで、やっていけばいいだけですね。
ーー現代の若者は何かを死ぬ気でやったりすることをかっこわるいって思ったりしている気がします。そういった抵抗はなかったですか?
昔は、もちろんあった。斜に構えてたことやっていましたよ。けれど、僕が映画を始めたのが遅いのが良かったというか。「そうして私たちはプールに金魚を、」を作ったのが33、34歳ぐらいで、人からダサいって思われそうだなと思っても、それを超えるぐらいどうしてもやりたいことがたまりすぎちゃってたからっていうのが大きいですね。そこまで本当に何も作らずにいたから、もう斜に構えてたら死ぬぞって思って。結局そうしないと、 自分が本当にいいと思うものが作れないから。何歳でやるにせよ、 人からダサいって思われようが、自分はマジでこれがいいっていうものを、作ること一択だと自分では思ってます。

命をかけて、作り上げる作品
ーー長久監督の作品は、映画にはあまり見られない「第四の壁」を超えるもの(カメラ目線)が多く見られるのですが、誰に向けて話しているんですか?
自分が映画を見るときもそうなんですけど、お客さんが何人いたとしても、常に映画は1対1だと思っています。だから、僕は映画を美的芸術の鑑賞とは思ってなくて、映画側から見てる1人のあなたに向けてど太い矢印をまっすぐ出しているものとして作っています。「あなた」に向けて言葉を言ってるから、第四の壁を越えるのはもう自然ですね。技術的にあえてそれをやろうって感じじゃなく、逆にやらないのは我慢してる状態です。「あなた」に向けてやってますからっていうのが、僕が思う映画というもののデフォルトで。
今日も、この秋撮ろうと思ってた脚本を整理してて。語る部分をドキュメンタリーっぽくしとこうかと思ったけど、「ええい別にどうでもいいわ! カメラ見て喋りゃあいいわ!」と。映画はそうあるべき、と思ってます。過剰な思考ですけど。
ーー長久監督ならではの表現が表れているシーンの一つに、食描写があると感じました。なにか意識されていることはありますか?
例えば、ラザニアのシーンとかがグロめに描かれていますが、僕が小学生の頃は両親が共働きだったから自然な描写なんです。グロくは描いてるんですけど、あれが不幸だと本当に思ってない。外から見たら不幸に見えるかもしれないですけど、自分にとってはデフォルトである価値観で、それが作品にも現れていたりするんだと思います。自分のデフォ感覚こそが意外とオリジナリティーというか、人様と違う価値観だから、それを定着させていくのがいいと思います。みんな感動するシーンで感動することはもうやってくれる人がいるから。自分のデフォ感覚のことを書いた方がいい。
他の人に作れるものは他の人に任せた方が良いです。自分しか作れないものを作るしかないから、それを作った方が精神衛生上も良いです。僕も、脚本段階だと良さわかんないって超言われるんですよ、ごじゃごじゃだから! これまとまってんの?とか「そうして私たちはプールに金魚を、」の時とかめっちゃ言われました。でも、大丈夫です! って言ってやるしかなくて。ゴールイメージは自分の中にできてても、脚本でも伝わらない時も結局あるから。本当に数を完成させるしかなくて。この人はこの脚本だという風になって、これがめっちゃよかったっていう、作品としてもう作りきるのを、数やるしかないのだと。それを、自分がマジでいいと思うものを守ってくっていう。
ーーそういった監督独自のスタイルはどんな経験から生まれたのですか?
学生の頃、専門学校行くって決めた時にイメージフォーラムで見た新藤兼人の「ふくろう」っていう映画があって、本当に何の情報もなく見に行ったんですけど。それが映画のルールを全然脱してて「これをやりたい」って思ったのが始まりでした。当時はすごく邦画っぽくて評価されそうなもの、これでぴあ(ぴあフィルムフェスティバル)獲るぞ!みたいな感じとか、ぴあ獲れなくても邦画のインディムービーっぽいぞ!っていうものを、ちょっと頑張って作ってたけど、評価されず。夢を諦めて、僕は就職をしたんですね。そこからは、広告の仕事をしていました。広告はたくさんの人の共感を得たり興味を惹くものを目的上作らなきゃいけないんです。10年以上やってたので、仕事としてはちゃんと伝わるものをいくつも作ってたんですけど、僕が本当にやりたい表現ではないということに改めて気づけて。「そうして私たちはプールに金魚を、」で久しぶりに自分が映画を好きに作れるとなった時は、人生で1回だけの、最後の映画作る機会だなと思ってたので。自分が信じる美徳だけを詰め込もうと思って作りました。だから結果、あの作品はそういうものになってるっていうか。構成とかも、当時映画的じゃないってすごい批判だったけど、僕はこれが正しいと思うんです、と。実際自分の美徳のために作ったから評価されなくても良かったんですけど、それが海外で評価されたので、これで、このままの姿勢で映画を作り続けてもいいんだと思って。その作り方、そのフィロソフィーで作ろうってことをぶらさずにっていうことを決めた感じですね。
多分学生時代に自分がやっていた映画のあのスタイルでちょっとでも評価されてたら、もうちょっと迎合スタイルだったというか、マジョリティー的に上手にやる監督スタイルになっていたと思います。 僕は今の作り方が自分的にはやっぱりいいと思ってるので、挫折して遠回りしてよかったって本当に思ってます。
ーー一度諦められた映画という道に、あらためて進もうと思ったきっかけはありますか?
映画を辞めてから、広告の仕事を10年以上やっている間に、映画をやりたいという気持ちが沸々と湧き上がってきたっていう感じです。だから、やりたくないことをやってたおかげでもある。今作るのが楽しいのは、きっと美大に入りたての学生がめっちゃ作りたい!みたいな気持ちと一緒だと思います。1年生の感覚に近いのが39歳で訪れてるって感じ。
でも、やってきた広告という仕事によって得た筋肉がめちゃくちゃあるので、経験を後悔してることはないです。「そうして私たちはプールに金魚を、」を作る時に、好きなPVを調べて、このカメラマンの人いいなと思って「初めましてなんですけど……」って連絡してスタッフィングに至りました。その時も、ちゃんと仕事をしてたからこそ得た信頼関係みたいなものはやっぱり大きかったかなとは思ってます。結果オーライかなと思います。今も新しい人ともちょっと入れたりしつつ、基本的には同じメンバーでやっていくのがいいなと思っています。 バンドとして。みんなで歩いていきたいなっていうのはやっぱりある。みんなも想像してないようなところに連れていけたら楽しいだろうなとは思います。
後編はこちら
◾️長久允
東京都出身の映画監督、映像作家、脚本家。2017年、短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞。それに続き、「蟹から生まれたピスコの恋」はサンダンス映画祭2024短編部門審査員特別賞(監督賞)を受賞。
◾️長久允監督短編映画2本だて上映「そうして私たちはプールに金魚を、」「蟹から生まれたピスコの恋」
期間:2024年6月28日(金)~7月11日(木)
場所:渋谷シネクイント
チケット:シネクイントチケット予約サイト