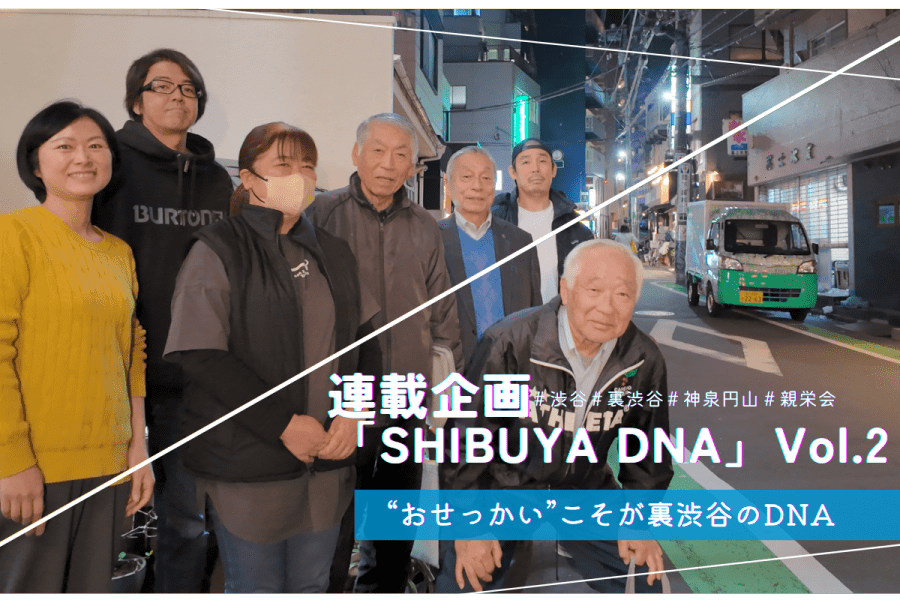「未来につながる渋谷のまちづくり」を目指し、活動している鈴木大輔です。
この渋谷新聞をはじめ、まなぶや、渋谷区SDGs協会、太平洋商事などの代表を務めています。
不動産に始まり、商店街、多くの団体役員、地域貢献事業、スタートアップ支援、SDGs事業、メディア運営、中高生企業支援などいろいろなことをやっています。
今回は、私が力を入れている、地域コミュニティへの貢献と、若者への機会提供、大人と学生が共創しながらビジネスをする仕組みづくりについてお話ししていきたいと思います。
将来へのビジョン、渋谷という街への思いなどをライターのなっちゃんに取材してもらいました。
「成長の土壌をつくる」

――最近の変化について教えてください。
「はい、今渋谷を盛り上げるための様々な事業があり、たくさんの学生と社会人が参加してくれています。そのベースとなるのが&&(アンドアンド)という組織があるのですが、”人材育成の場”、”人材成長の場”として、&&を再定義したという感覚があります。もともと”機会提供”という軸でやってきたんですが、最近は”人の成長”というところを主軸に置きたいと思うようになったんです。
若い人たちが、自分の意思で成長していく。そのための土壌を整えたいというのが、今の自分の中での明確なビジョンです。実際、現場で働いている高校生や大学生、あるいは海外からのインターンたちの姿を見ていると、『ここが人材のインフラになっているな』と感じる瞬間が増えています」
――具体的には、どのような環境や仕組みが生まれてきているのでしょうか?
「たとえば、過去に中学生のころに『まなぶや』に参加していた子が大学生になって戻ってきて、さらにその友達を紹介してくれる。最近も、ある大学1年生が自分の友人を6人連れてきてくれました。その中にはシンガポールで7年間暮らしていた、英語が堪能な子もいます。人材を募集していないのに、自然と人が集まってくる。しかも優秀な人材ばかりです。これって本当にありがたいことで、自分の中では『鳥肌が立つ』ような現象なんです。採用コストがゼロに近いだけでなく、人と人との信頼でネットワークが回っているのを感じます」
――外国人インターンの受け入れについても進んでいるそうですね?
「そうなんです。たとえば、香港やアムステルダムからの大学生インターンを受け入れるようになりました。これまでは『英語が話せる人がいない』という店舗の課題がありましたが、今では多言語対応ができるチームが自然と形成されてきています。その背景には、『渋谷で実践できる場』があるからだと思います。単なるバイトではなく、英語を使いながら接客をし、現場で学べる。それが大きな魅力になっているようです。今後はこの流れをさらに仕組み化して、インターンの受け入れを本格的に行っていきたいと考えています」
――渋谷という立地とそこで得られる多様な機会について、どのような魅力や効果があると感じていますか?
「渋谷の一番の魅力は、多様なフィールドが揃っていることだと思います。弊社の活動だけを見ても、ローカルメディア渋谷新聞・表参道原宿新聞などのライター、不動産事業、旅館業、民泊などの建築設計、地域連動のイベント企画、インバウンド事業など、関われる分野は本当に広い。渋谷という立地だからこそ、多彩な人材が集まり、それぞれが挑戦できる受け皿が用意できるのだと感じています。
最近では、世界を見据えて起業しているような学生もプロジェクトに加わってくれていて、その存在が、周囲に良い刺激を与えてくれるんですよね。また、普段あまり関われないような、議員さんとのイベントや渋谷区との連携事業なども増えています。まさに渋谷全体にネットワークがどんどん広がっています。それが、個人の成長だけでなく、組織全体の活性化にもつながっていると実感していますね」
――大輔さんは、若手にどんどん事業を任せていくところがありますよね?
「はい、それは意識的にやっています。僕も親の会社を継いでそれを発展させようとい、自分で事業を立ち上げてきたというところもあります。なので、どんどん任せて発展させて欲しいという思いが強いんです。もちろん、最初からうまくいくわけではないです。でも失敗してもいい。そこで得られる経験が、その人の財産になると思っているので、責任あるポジションにどんどんチャレンジして、実行していって欲しいと思っています」
――そうしたチャレンジが「成功体験」につながっているのでしょうか?
「まさにそうですね。たとえば、紬という着物ショップでは、以前は月に数万円ほどの売上しかありませんでしたが、いまでは月商数百万円を超えるまでに成長しています。みんなで、何度も試行錯誤し、失敗も重ねながら改善してきた結果です。これこそが成功体験だと思います。小さなことでも、自分で考え、行動して、成果が出たときの喜び。それが人を育てると実感しています」
20年以上渋谷を見てからこそ語れる数字じゃ測れない“感覚の経営”

――多数の事業を展開される中では、最初は売上が低かったり撤退を考えた事業もあると聞いています。どのような判断基準で経営をされているのでしょうか?
「正直に言うと、最初から明確な数値基準を設けていたわけではないんです。たとえば『この事業が1,000万円赤字になったらやめよう』みたいな撤退ラインを引いていたら、多分、いくつもの事業は途中で終わっていたと思います。
ただ、それでも続けてこられたのは、自分自身が渋谷で20年以上現場に関わってきた中で得た”直感“と”経験値“があったからです。いまは苦しくても、これは絶対に必要なんだと信じていたから。だから、もう少しだけ我慢しようと思える。そういう判断の積み重ねでしたね」
――「根拠のない自信」とよくおっしゃいますが、不安はどうやって乗り越えているのでしょうか?
「そうですね。『根拠のない自信』があると自分でも思っています。ただ、それはデータではないけど、実は確かな経験の裏付けがあるんです。20年という時間の中で、渋谷の街がどう変わってきたか、何が求められ、何が淘汰されたかをずっと肌で感じてきました。そのリアルな感覚が、数字やデータには表れない『根拠』になっているんですよね。
ですが、もちろん実際は、不安はもちろんあります。でも、『やってみないと分からないこと』って多いじゃないですか。だったら、やってみてダメだったらまた考えようっていうくらいのスタンスで進み続けたい。そう思ってます。経営って、結局は調整の連続なので、完璧を目指すよりも、まず動いてみる。その結果を見て、また次の手を打てばいい。そう思って動き続けています。」
――大輔さんのモットーもとにかくDOする。「DDDD」でしたもんね。現在、複数の事業を展開されていますが、それらはどのように連携し、シナジーを生んでいますか?
「一見バラバラに見えるかもしれませんが、実は全部がつながっているんです。不動産事業部で物件を確保して、それをバーや民泊、プロモーションに活用する。その結果、毎月数百万の収益が見込めるようなスキームが生まれています。
長年、渋谷エリアで不動産をやってきたことで、良い物件を早い段階で押さえることができます。たとえば、通常は売買や仲介で収益を得るだけですが、そこに旅館業や民泊などの事業を組み合わせることで、物件の価値を高め、利回りを向上させることができます。
最近だと、神宮前や代官山で新しい旅館業・民泊物件を契約しました。センター街では店舗も増やしており、これは単なる小売りや飲食ではなく、プロモーションにも使える、イベントにも使えるという、多用途な展開を想定しています。そうすることで、従来の「貸す・借りる」だけじゃない不動産の使い方ができるんです。不動産で得た“場所“を活かす“人材“がいるのでできる仕組みですね」

――今後はどのようなことを計画されていますか?
「渋谷はインバウンド旅行者が多い割に宿泊施設が少ないので、3年で民泊事業を20件まで拡大する計画も立てていて、着々と準備を進めています。また、代官山でシェアバーも計画中です。“一日オーナー制度“を取り入れた新しいタイプのバーです。日替わりで様々なスタッフが運営できるようにして、普段の業務とは違う接客や経営体験ができる場にしたいと思っています。着物のTSUMUGIのスタッフだったり、旅館業・民泊チームだったり、関わってくれている仲間たちが『今日は私のバーの日です』ってお客さんを迎える。それを見にきてくれる仲間や地域の人たちがいて、自然とコミュニティができていく。そんな、ちょっと温かくてユニークな場所を目指しています」
――大輔さん個人として、最近の組織の変化やご自身の考え方の変化について、どのように感じていますか?
「最近は、人材育成や地域貢献に対する思いが、以前にも増して強くなってきている気がします。社員も増えてきて、ひとりひとりの関係性と成長への機会提供を大事にしたいと思っているんです。
また、新しい事業が立ち上がるたびに、その事業に関わる若手が成功体験を積んでいくのを見るのは、僕にとってもすごく嬉しいことです。こういう体験を通じて、人も組織も育っていくんだなと、あらためて実感しています」
――今後の渋谷のまちづくりに対して、どんな構想を描いていますか?
「一言で言えば、”三方よし“のビジネスをもっと増やしていきたいと思っています。地域の人、来訪者、そして我々運営側の三者が、すべてにとって良い状態をつくる。今まではソーシャルとビジネスを分けて考えていたのですが、それを融合していく段階に入ったと感じています。
最近では、”センター街のスキマバイト“という多言語人材の即戦力派遣の構想も立ち上がりました。地域店舗の『英語が話せるスタッフがいない』という課題に応え、インバウンド対応を強化する仕組みです。若者が実践を通じて語学と接客を学び、地域にも貢献できる。そんな仕組みを作りたいと思っています」
一緒に渋谷の未来を創る仲間を募集しています
学生の皆さん、企業・自治体の方々、渋谷の未来を一緒に創る仲間を随時募集していますので、お気軽にご相談ください。
→https://daisuke-shibuya.com/about/